判定は原則として外観調査であり建築物自体を調査するものです。設備関係で気が付いたことがありましたら、調査表のコメント欄に記入してください。
17.調査項目の「1」、「2」、「3」の調査順を、「1→3→2」としている理由は何か。
事前に落下危険物を調査することにより、調査中の判定士の安全を確保するためです。
18.「調査2」及び「調査3」のうち、大きい方で危険度判定をすることになっているが、「調査3」の看板、機器類でCランクになった場ち合は、その建物を総合評価で「危険」とするのは現実的ではないように感じるが、どうか。
応急危険度判定は二次災害を防ぐことを目的としているため、落下危険物がみられる場合、建築物に損傷がなくても「危険」と判定してください。
19.「周辺地盤」の周辺とは、どの位までのエリアをしめすのか。
調査対象建築物の敷地に影響を及ぼす範囲と考えます。手帳P33を参照してください。
20.死亡原因の多い石塀、ブロック塀の判定基準は、コメント欄への記入で良いのか。
石塀、ブロック塀の安全性は、建築基準法施行令第61条(組積造のへい)や令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)の基準を参考に、目視できる範囲のなかで判断してください。 また、調査表には「3 落下危険物・転倒危険物… もっと読む »
21.隣接地盤が”不明確”なのに、なぜBランクなのか。”不明確”な場合はCランクにすべきではないか。地盤は「大丈夫」か「だめ」かの二通りではないのか。中間はないと思うが・・・。
地盤の調査については、被災宅地危険度判定調査により具体的な調査が行われます。応急危険度判定調査における周辺地盤の調査は、対象建築物への影響の度合いや宅地の概況を把握することにより、その後の宅地判定活動の判断材料とすること… もっと読む »
22.1敷地内に複数棟の建築物がある場合、敷地全体でみるのか、棟別でみるのか。
棟別で判定ステッカーを掲示するのがベストだが、母屋の判定ステッカーのコメント欄に対する注意事項を記入し、周知する方法もあります。 地域性が影響してきますので、判定先の市町村の応急判定実施本部の指示に従ってください。
23.判定標識は、共同住宅の場合や建物の大きさ形状に関わらず1棟1枚か。
1棟につき一枚が原則ですが、共同住宅や規模の大きい建物で、出入り口が数箇所ある場合は、エントランスホール入り口や共用玄関など、居住者や利用者のみならず歩行者などにも目立つところを数箇所選び、安全で見やすい部分に標示してく… もっと読む »
24. Aランクの場合、内観調査を行うことが望ましいとの説明があったが、居住者の了解を得て実施する必要はあるか。その際、内壁にクラック等があった場合は、判定ランクを変えるのか。
居住者の了解を必ず得てください。不在であれば、外観より判断をしてください。その際、内壁にクラック等があった場合は判定ランクを変更してください。
25.木造の場合、調査の上位3-①でCランクとなった場合(Cと確定するので)それ以降の調査は省略してよいか。
最後の調査項目まで、安全な場所で外観検査を行い、確認できる範囲の被害状況を判定調査表に記載してください。
26.湿式のモルタル等がほとんど剥落している場合、それ以上の落下の危険は無いので、安全ではないのか。
落下物が無く、危険が認められなければ「Aランク」の判定となります。
27.傾斜測定を「×/100」にしないのか。
木造の傾斜は1/60、1/20であり計算しやすい「×/120」を採用しています。また下げ振りも1.2mで印を付けてあります。(手帳P55)
28.不同沈下を壁の傾斜で測定するとのことだが、S造のラーメン構造で明らかに不同沈下でなく、柱が傾斜している場合はどうするのか。
不同沈下の認められない柱の傾斜の場合、基礎と柱脚、または柱脚に構造的な破断等が予想されることから「危険」と判断されます。この場合計測は不要です。
29.乾式の外装材で躯体が覆われ、建築物の構造駆体の損傷が判定できない場合はどうするのか。
判定は原則として外観調査としますので、外装材等の被害状況から判断し、判定してください。
30.鉄骨造等で火災にあっているものの判定は行うのか。
判定するにあたり特に危険なものは実施しません。判定士の身の安全を第一に考えてください。
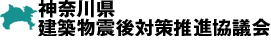
最近のコメント